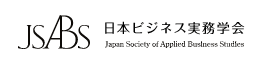執筆要領に指定される書式(ビジネス実務論集に掲載されるフォーマット)に著しく合致しない場合、原則、投稿を受付けない。
- 原稿
A4判(縦版)の用紙に、原則としてワープロソフトを用いて2段組み横書きで書き、原稿の枚数は要旨・図表・注等すべてを含めて12枚以内とする。 - 原稿の字数
1 ページの標準の字数は23文字×42行×2段組みとし、用紙の上下左右の余白は、上下が30mm、左右が22mmとする。ただし、表題・著者名・所属機関名については2段組みに設定する必要はない。また、サイズの大きい図表など、2段組みにすることが適切でないと認められるものについては、段組みを設定しなくてよい。なお、執筆用のテンプレートは、本会のWebサイトからダウンロードして使用する。 - 文字の大きさ、フォントおよび位置
文字の大きさ、フォントおよび位置は次のとおりとする。表題(和文): 18ポイント(MS明朝体・太字:中央揃え) 副表題があるとき:副表題(和文): 14ポイント(MS明朝体:中央揃え) 著者名(和文): 14ポイント(MS明朝体:右揃え) 所属機関名(和文): 12ポイント(MS明朝体:著者名の後に括弧して記載) 表題(英文): 14ポイント(Times New Roman:中央揃え) 副表題があるとき:副表題(英文): 14ポイント(Times New Roman:中央揃え) 著者名(英文): 14ポイント(Times New Roman:右揃え) 所属機関名(英文): 12ポイント(Times New Roman:右揃え) 要旨の見出し: 10.5ポイント(MSゴシック・太字:中央揃え) キーワードの見出し: 10.5ポイント(MSゴシック・太字:左揃え) 章、節: 10.5ポイント(MSゴシック・太字:左揃え) 項: 10.5ポイント(MS明朝体:左揃え) 本文(和文): 10.5ポイント(MS明朝体) 本文(半角英数字): 10.5ポイント(Times New Roman) 注・参考文献の見出し: 10.5ポイント(MSゴシック・太字:左揃え) 注・参考文献(和文): 9ポイント(MS明朝体) 注・参考文献(英文): 9ポイント(Times New Roman) - 表題と著者名
原稿の冒頭には、表題、著者名、所属機関名を記載する。また、これらについて英文も併記する。共著で論文を投稿する場合の著者順は、投稿される論文内容に最も貢献した者を筆頭著者とする。ただし、著者全員が論文の内容に関する責任を負う。また、著者の人数は、投稿論文の内容に貢献し責任を負う適正な数とする。
なお、査読用原稿には著者名および所属機関名を記載しない。 - 要旨
本文の前に要旨(800 字以内)と、キーワード(5 つ以内)を記載する。 - 文字
文字は常用漢字・現代かなづかいによることを原則とする。また、欧文は活字体を用いること。
外国語には、できるだけ訳語を付けること。外国の地名・人名は原語を用いること。 - 本文
本文において章・節等の記号を付ける場合には、次のように記すこと。章にあたるもの 1.見出し(全角)
節にあたるもの 1.1 見出し(1.1は半角、その後のブランクは全角)
項にあたるもの (1)見出し(全角)なお、本文の構成の一例を以下に示す。
(1) はじめに/序論
例えば、研究の背景、関連する先行研究、研究を始めた動機、研究の目的を説明する。また、論文等の要約と得られた成果を簡潔に説明する。既に発表された論文等があり、その内容をもとに発展させた論文等を新規に投稿する場合は、もとの論文等を参考文献として明記し、文章中に関連を明記すること。
(2) 本文内容
研究の方法(実験方法、分析方法等)、得られた結果、知見、先行研究との比較、考察などについて、説明する。
(3) まとめ/結論:
得られた結論や成果を簡潔に記す。また、残された課題があれば簡単に書く。 - 図表
図・表は一緒にし、記号は次のように記すこと。例)図表1 図表2 図表3
図表タイトルは図表の上に記すこと。
図表は、印刷用版下として直接使用できるものであること。特に文字の大きさが小さくて読めないものは提出しないこと。 - 注
注は、可能な限り本文中に組み入れること。やむを得ず脚注を記述する場合は、できるだけ少なくした上で、 (1)、(2)のように注記の一連番号を参照箇所の右肩に書くこと。また、注記そのものは、本文の最後に一連番号を付けてまとめること。その際、Microsoft Wordの文末脚注機能は使用しない。 - 参考文献
引用・参考文献の記載形式は以下の例による。引用の場合は、当該箇所の頁も記すこと。
なお、順番は、著者名の姓のアルファベット順に並べること。同じ著者の文献が複数ある場合は、発行年順に並べること。和文・英文で分けない。同じ著者でかつ同じ年代の場合は、(山田2018a)のように小文字のabcを年代に追記して区別できるようにすること。
また、本文中で触れる場合、著者人数によって下記のような表記とする。(1)単著の場合:(山田 2025)(Yamada 2025)
(2)2名の著者の場合:(山田・鈴木 2025)(Yamada and Suzuki 2025)
(3)3名以上の著者の場合:(山田ほか 2025)(Yamada et al. 2025)■ 日本語単著書(単行本)の場合
≪著者名(出版年)『書名』出版社名≫
例 濱口桂一郎(2021)『ジョブ型雇用社会とは何か-正社員体制の矛盾と転機』岩波書店.■ 日本語共著書(単行本)の場合
≪編者名(共著者名)(出版年)『書名』出版社名≫
例 水原道子・大島武編著(2017)『新版 ビジネス実務総論』樹村房.≪分担執筆者名(出版年)「分担執筆題名」編者名『書名』出版社名、分担執筆箇所:所在ページ≫
例 牛山佳菜代(2021)「新しい自己分析」見舘好隆[監修][著]・保科学世ほか著『新しいキャリアデザインーニューノーマル時代をサバイブする』九州大学出版会、第5章第2節:pp.110-116.■ 日本語雑誌論文の場合
≪著者名(出版年)「論文名」論文集(雑誌)発行機関名『論文集名(雑誌)名』巻(号):ページ≫
例 湯口恭子(2024)「ロールモデルが大学生のキャリア探索に与える影響-家族や友人・知人と、著名人・架空の登場人物とを比較して-」日本ビジネス実務学会『ビジネス実務論集』第42号:pp.41-51.■ 欧文著書の場合
≪著者名(出版年)『書名』出版社名≫
例 Dalkir, Kimiz(2023)Knowledge Management in Theory and Practice, 4th edition, The MIT Press.■ 翻訳文献の場合
≪原著者(翻訳者訳)(出版年)『書名』出版社名≫
例 ダックワース、アンジェラ(神崎朗子訳)(2016)『やり抜く力GRIT(グリット)―人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』ダイヤモンド社.■ インターネット資料の場合
≪サイトの運営主体.情報テーマ.(サイトURL).情報入手日.≫
例 厚生労働省.「働き方改革」の実現に向けて.
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/index.html).2024.12.1取得. - 謝辞
謝辞に記す者は当該研究に対して助言や協力を受けた者を記す。
なお、謝辞の部分を除いたものが、査読者に送られる。 - 引用
他人の文章をそのまま引用した場合は、部分全体を「 」でくくり、必ず出典を記す。
断片的な引用によって著作者の主張と異なると誤解されるような記述をすることは、著作者人格権の侵害とみなす行為となる恐れがあるので注意すること。 - 投稿手続
原稿は、この執筆要領に従って執筆し、「投稿責任者(会員であること)」が、編集委員会が指定するメールアドレスを通して投稿をする。その際、以下の提出が求められる。
(1) Microsoft Wordで作成した原稿オリジナル(図表、写真等も含む電子ファイル一つ)とそれをPDFファイルにしたもの
(2) Microsoft Wordで作成した原稿オリジナルから、著者名や所属機関名、および謝辞など著者が想定される文章を削除した査読用原稿とそれをPDFファイルにしたもの
なお、審査の結果掲載を認められた原稿については、改めて当初の書式に即した最終原稿(表題、著者名、所属機関名の英文での記載を含む)に加え、英文要旨(200~300語で、表題も含め、ネイティブ・チェックを受けたもの)を提出すること。 - ビジネス実務論集への掲載料は無料とする。
- 原則として著者校正は初校のみとし、校正の際の原稿への加除は認めない。
注:所属または関連機関の倫理委員会の承認を得ることや、「教育開発研究」の内容としては、主に以下の4点について記述することが望ましい。
- 開発の背景
- 開発の目的
- 開発した成果・教育プログラムの内容
- 教育プログラムの評価・考察
改定日
本要領は、2019年6月1日から改訂する。
本要領は、2025年5月31日から改訂する。
論集執筆用フォーマット
以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。